
オーディオ特化型SNSのサービス終了
マニアに愛されたオーディオに特化したSNS「ファイルフェブコミュニティ」が昨年サービス終了しました。
ツイッターやFacebookと違い、日記ページは各マニアの長文、画像やリンク付きのまとまった投稿が可能だったことから、濃いマニアには大いに愛されたサービスなので終了は残念です。
自分やほかのマニアの投稿を過去にさかのぼって簡単に読み返せる(もちろん検索も可)なので、ツイッターやFacebookのように過去の投稿を読み返すのに不便ということがなく、ストック型のサービスとして他にない利点がありました。
つまり、独自にブログなどを持たなくとも、その人のプロフィールやシステム構成、システムや考察・研究の変遷がまとまって公開・共有できたわけです。
※グーグル検索にもかかるので、登録していないユーザーでもそうした知識やノウハウの共有に参加できました。
このような利点があったため、マニアの中には惜しまれる声が続出しました。ついにその中から有志が立ち上がり、類似機能を持つサイトを独自に立ち上げました。
それが「フィルム・コミュニティ」https://philm-community.com/です。
新サービスに引き続き熱いマニアからの投稿が
新サービスの「フィルム・コミュニティ」は、管理画面の操作がまだ慣れないせいか少し大変だったり、日記に外部リンク禁止という不可解なルールがあったりして使いにくい面もないではないです。
しかし、このようなサービスをボランティアかつ参加無料で立ち上げたというのは、とても称賛に価すると思います。頑張ってほしいです!
「のびー」さんの素晴らしい投稿
その「フィルム・コミュニティ」における2022年5月6日(8月29日修正)の日記投稿に目が留まりました。
日記のタイトルは「PCオーディオの常識もろもろ」というものです。詳しい内容は、リンク先をお読みください。
PCオーディオを始めたのは2005年頃
のびーさんの日記には、のびーさんがPCオーディオを始めたのは2005年頃とあります。
少し前に、私がPCオーディオを始めたころを振り返った動画を公開しました。少し早く始めたようですが、似たようなものです。
2005年からPCオーディオに関するまとめ記事を公開し始めました。今となっては古い内容ですが、一応歴史としてページは残して(旧サイトより移植)います。
特に感心した「PCオーディオ常識の変化」
日記の後半の
ずっと信じていた「PCオーディオの常識」の反例が多く出て来てしまった
フィルム・コミュニティ、のびーさんの日記
から始まります。
具体的に従来の常識と、それが変化したのかしないのか、一つ一つ考察や説明が加えられています。
ここ十年くらい、それまでの常識がいくつか覆りつつあるというのは、大いに共感できます。
のびーさんの指摘と当サイトの考察まとめ
では、ひとつづつのびーさんの指摘をご紹介しつつ、当サイトの考察も加えてみたいと思います。それぞれの意見を否定しあうわけではなく、同意できることや若干違った意見となる場合でも、今後のPCオーディオの発展に繋がればという趣旨です。
低スペックは低ノイズ
以前の常識
CPUのコア数は少ないほど、CPUクロックは遅いほど、メモリー容量は小さいほど良い
最近の傾向
これに対するのびーさんの経験・考察による新しいトレンドは
微細化が進んだ最新のPCでは、高スペックの部品でノイズが気になることは無く、余裕度の高さのメリットの方が大きいようです。
です。
この問題は、上の動画でもテーマにしましたが、正直よくわかりません。のびーさんと同様に、最近多くのマニアが経験上「速い方が良い」と指摘しているのは感じています。
当サイトでは、調査や実験をしまくった訳ではないですが、「速度を上げれば上げるほど良い」という訳ではなくて、OSや使用ソフトウエアに対するバランスで、ある性能で頭打ちになるということかなあ、とアバウトに推測しています。
本当に「速い方がよい」であれば、多くの上級マニアが取り組んでいる「ラズパイオーディオ」やオーディオシステムに繋ぐそうしたシングルボードPCでは、いくらLinuxの軽いオーディオ再生専用ディストリビュートを使うとしても、飽き足らなくなるのではと思います。
また、オーディオ機器(専用機)のネットワーク再生機能などに搭載されているCPUや、類似の働きをするFPGAとかマイコンは、今時のWindowsやMacに搭載されているCPUよりも遥かに遅いと思われ(例外もありますが)ます。
そこを速くすればよいのであれば、ハイエンド機などはこぞって高速CPUを搭載するのではと思ったりします。
しかし、現実には多くのマニアが速くして音質向上したと報告しています。一般的なデスクトップオーディオの「PC+USB」とか、その発展型であればそうなのかもしれません。この問題は、今後も注視していきたいと考えています。
分散は力
以前の常識
サーバー、コントロール、オーディオ出力の3台のPC(もしくは端末)が必要で、機能分散・負荷分散の効果は大きい。
DLNAやOpenHomeなどのネットワークプレーヤーでは分散が前提になっており、PCオーディオでも操作性に加えて音質面からも分散構成のメリットが強調されてきました。
最近の傾向
のびーさんの意見
低スペックPCを複数使用するより、高スペックPC1台の方が良い。機能分散は通信を伴うことからどうしても構成が複雑になります。新しいPCを簡単な構成で再度聴いてみると結構いけます。
ここは、当サイトはもう少し幅広く受け止めています。
コントロールは、利便性の点が大きいことから別として台数計算から一旦外します。
「サーバー」「オーディオ出力」という構成は、NASとDLNA(改良型のOpenHome含む)という従来型のもので、最近はそれに加えて「ファイルサーバー」「ファイル操作&再生エンジン」「オーディオ出力」というRoonのような2-3台、あるいはそれ以上、それ以下の柔軟な構成にトレンドが変化していることが影響しているように思います。
サブスクの音楽ストリーミング(特に最近はハイレゾ)が一般化してきた影響もあると思います。
オーディオ専用機でも、RoonやDirettaがDLNAに置き換わりつつあるのでは?と感じています。
「ストリーマー」とか同義の「ブリッジ」という新しいオーディオ機器が次々発売され、それらを繋ぐのに「光LAN接続」や「オーディオ専用ハブ」の人気が高まっているのは、分散化の定着現象の一端ではないかと思ったりもします。
少なくとも、プリメインアンプよりも上級者がプリアンプとメインアンプを分けることを好むように、USBDACが直結できるデスクトップオーディオ以外は、ストリーマーとDACは別の方が好ましいかなと考えています。

Linuxを駆使する上級マニアも、Roonブリッジ、Direttaホスト、AoE(Audio over Ethernet)を取り入れる人が少なくありません。
とはいえ、Linuxオーディオで伝統的なMPDというのは、PC2台構成で、外観上はDLNAに似ていますが、人気は衰えてないようです。
※MPDはファイル格納庫(NASなど)との間が、バルク転送なのでDirettaやRAAT、JPLAYは不要という意見も聞いたことありますが、どうなのでしょう?
処理の分散化は、特定の機器への処理集中を軽減し、ノイズや遅延及び瞬間的な電力消費を避けられるというのは、デジタル処理の原則として違っていないように思います。CPUが高性能化してスレッドやプロセスが多数化したため、物理台数や部品を減らしてCPU内部で分散化した方が、オーディオ処理程度であれば結果が良いという事でしょうか?
結局これも結論は出せないのみならず、当サイトの意見も分裂気味でまとめきれない状態です。今後のオーディオ界の進展やマニアの建設的議論を待つ他ないかなと感じています。
OSやアプリは軽いほど良い
以前の常識
引用
「Windows < 汎用Linux < 専用Linux」※軽いほど良い
「Windowsの場合は、プロセス数、スレッド数が少ないほど良い」
最近の傾向
のびーさんの意見は
同じOSなら不必要なプロセスを止めてCPU稼働率を下げた方が良いという鉄則は、まだ有効だと思います。
ここは同意見で、あまり変わっていないと思います。
のびーさんは、感覚的にWindowsの音が好き派ということですが、私は逆にLinuxの音が感覚的に好きで、その違いはあります。
デジタル・インターフェイスが大切
以前の常識
「SPDIF < USB < I2S」主義主張はともかく、多くのDACがUSB接続を前提としています。
最近の傾向
のびーさんの経験・考察は
多くは理論的に説明がつくし、経験上も正しいものです。ただ、総合的な音質にどれだけ影響するかは実装状況により大きく変化します。理論的に説明がつかないものでも自分が適当な理論を知らないだけかもしれません。
ここも、10年前と変わらないという部分は同意見ですし、経験・考察にも異論はありません。
少し当サイトなりに整理してみます。
SPDIFは規格が古すぎて、これ以上の性能向上は見込めない印象ですが、現在のハイレゾの192/24(例外的にそれを上回る音源もありますがとても少ない)という範囲はカバーできていて、新しい規格の映像伝送兼ねたHDMIなどよりメーカーもマニアも扱いやすいと思います。
USBは、以前はかなり良くないといわれましたが、改良やノウハウが進み、機能上はより高いサンプリング周波数・Bit数も送れるのでSPDIFより上と思います。
音質は実装次第で、通常音源ならベースに優劣はない印象です。
I2Sは、ベースの力は、上記の2つを上回りますが、伝送距離が短く、弱点も感じられます。
当サイトとしては、できるだけ多くのインターフェースを積んだ機器が望ましいとは考えており、活用法はユーザー次第がよいなと思っています。
電源は容量よりも低ノイズが大切
以前の常識
「スイッチング電源 < リニア電源 < バッテリー電源」 音楽再生専用PCは負荷変動が小さく、電源も瞬時電力供給能力より低ノイズが大切と考えられていました。
最近の傾向
のびーさんの経験・考察は
微細化が進んだ最新のPCでは、高スペックの部品でノイズが気になることは無く、余裕度の高さのメリットの方が大きいようです。高スペック部品を余裕をもって使用するためにリニア電源から最新のATX電源に変更すると更に良くなりました。
電源に関しては、オーディオの肝であり、ハイエンドメーカーでも巨大なトランス搭載でリニア電源にこだわるメーカーも、Linnのように早い時期からスイッチング電源を取り入れそれの改良に努力するメーカーもあります。
当サイトでは、音質の面よりも、実用上PC(500Wを上回るような今時のデスクトップ)のバッテリー駆動やリニア電源は大変なので避けてきた傾向であります。
小型PCであれば、ノイズ周波数の高いGaNが音質的に良いのではということで、以下のような動画を公開しています。
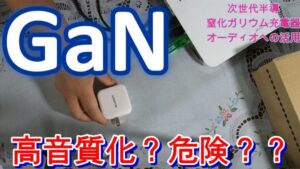
大型PCに搭載可能なGaNのATX電源が、すでに発売され、一部オーディオマニアが取り入れているようです。
今後は、こうした大型PCに対応するGaN電源のコスパがよくなることを期待します。
その他&付け加え
日記でのびーさんが指摘しているその他いくつかの点は、特に異論も付け加えることも有りませんでした。
「現時点でパーフェクトな再生ソフトは見当たらない」
「USB DDコンバーターは結構いけます」
一方で、当サイト独自に、常識が変化したことが思い当たりました。
以前→「ビットパーフェクトなら音に変化はないので、リッピングはパーフェクトにできる(補完がかからない)機器とソフトを使用しよう」
昨今→「デジタルファイルとしては同一なはずなのに、リッピングで音が変わる」
その後、コピーするとアナログのように劣化するとか、デフラグやフォーマット変換すると高音質化するとか、クラウドを通すと元に戻る、とかいろいろな意見も見かけました。理論や何が正しいかはわかりませんが、「音が変わる」という認識が昨今のトレンドのように思います。
まとめ
今回のように「PCオーディオ」で括るか「デジタルオーディオ」と広げるかでも、いろいろニュアンスも変わってくるように思います。
のびーさんの日記には、常識の変化とは別に他にも現段階で取り入れているノウハウや考察が記されていて、とても参考になりました。
まだまだ当サイトとしても、オーディオマニアの世界もメーカーも不明な点は多く、考え方やトレンドは変化していくと思います。
より良い向上に向けて、当サイトの情報共有が少しでも役立つことを願っています。
この記事の動画版も公開しました
同じテーマでの解説動画をYouTubeに公開しました。ブログには記載しなかった内容も一部含まれます。ぜひご覧ください!
動画をご覧になったkei furakiさんの詳細リポート
ゲーミングPCやオーディオPCを過去8台は組んできたというkei furakiさんが、詳細な長文報告をYouTubeのコメント欄に寄せていただきました。コメント欄では、読む人も限られるので、ご本人の承諾を得てこちらで紹介させていただきます。
※以下kei furakiさんの文章となります。
core2duoの頃から自作PCを8台くらい組み立ててわかったこと
core2duoやcore2quadのDDR2の時から自作PCをやってきて8台くらいは組み立てやってきました。
本格的にオーディオPCを考え始めたのは去年からオーディオ製品を買い始めてからですが、性能が高ければパフォーマンスはいいですが、オーディオ的な考え方をすればノイズというワードは出てきてしまうので、安定動作の範囲が一番無難かなとは思っています。
CPU温度でパフォーマンスの安定度は変わるのでゲーム使用高負荷時に60℃近くは普通に考えていますが、それ以外の負荷のかからない状態のときは30℃~上がっても45℃以下を目安にしています。
今のCPUではデスクトップ向けでもCPUをファンレスで5Ghz安定動作もできるらしいですが、ファンレスか静音簡易水冷辺りで3GHz~4.5Ghzを固定クロック動作でいいとは思います。CPUとメモリをOC動作で音の空気感の違いはあると思います(メモリとの応答タイミングもあるので良し悪し含めて変化すると思います)。
今はaudirvana originで再生していますが、会社が推奨しているカーネルストリーミング再生よりASIOの方が自分の環境では聞えがいいです。自分の環境でもOCして周波数を上げたりすると出だしの音は高クロック時の方が音は良い感じに聴こえます。澄んだ音で空間的な広がりや音の制御も上がっていたと思います。
自分はメモリの動作も重要だと思っています。ネットゲームなどは応答速度を速くして長時間やってもパフォーマンスが落ちないようにCPUクロック~電圧調整、メモリタイミングなど体感的に感じられるように設定していました。
安定品質であればプチフリーズは起こらないようにしたいですね。
メモリ込みでの安定動作はメモリーベンチマークソフトを一定時間おきに数回使っての確認もできますが、ゲーミング向け用途でなければ圧縮解凍ソフトのWinRARで多めで小分けされた画像ファイルや音楽ファイルを10分または30分から1時間圧縮解凍で予測時間とのブレを比較してみるのも動作確認としてはいいと思います。SSDが安定価格で普及し始める時代まではメモリの違いで動作の差は激しかったです。
オーディオPCにおススメのCPUとメモリ
オーディオ製品分の消費電力も増えたので今は低消費電力志向ですが、消費電力を気にしないのであればCPUはintelのKモデル(クロック固定で安定して動作は合わせやすいです)、メモリはネイティブ動作でセンチュリーマイクロ辺りだと相性トラブルも少なく全体的に動作が安定します。安定ラインであればドライブはPioneerかなとは思います。韓国製品より静音性もありますし。
CPUはintelとAMDがありますが、メモリを入れての動作を考慮すると自分はまだintel推しになります。
DSDフォーマットでCPU性能差は気になりますが、自分が使っているCPUが3770kと9700無印で1コア辺りのパフォーマンスが3770kが高く5Ghzで動作可能。コア数は多くても9700が無印な為4.4Ghz~4.5Ghz辺りが安全ラインでマルチコア処理にならないと差が埋まらないです。
メモリーもDDR3とDDR4の差がありますが情報量が多くない限り応答速度の速いDDR3の方に分があったりします。PC起動も3770kの方が速いです(泣)。
パフォーマンスとしては高クロックは伊達じゃないという結果になりました。
大まかな構成はcpu-3770k メモリCORSAIR CMD16GX3M2A2400C10 マザボMSI z77 Mpower
cpu-9700 メモリG.SKILL F4-3200C15D-32GTZR マザボASUS z390-f gaming
と世代差もありますが単純性能の差だけはクロックとメモリレイテンシ含めて埋まらなかったです。
DDR4で組んでなかったので取り敢えず組むかと年数差もあり楽勝と思って安易に組んだ失敗例です。
オーディオPCの電源について
電源のファンレスは比較的値段が高いので、妥当な価格で出力の高い物でいいとは思います。
ワット数の高い方が高負荷時にも安定した動作パフォーマンスをしてくれるのは多いと思います。ただオーディオ用であれば高負荷時で使う状況はあまりないかもしれないので500w、600wの物でも十分かとは思いはします。
自分はゲーム主体だったのでワット数高めの物でも消費する電力は基本変わらないので長い期間安定して使える850w~1000w以上の電源で組んできました。今はもうないですがHuntKeyというメーカーの1200w電源を11年位使っていました。ゲーム使用でパフォーマンスは落ちることもなく使えていたのですが、10年以上使ったし安全の為に10年物よりはマシかなと思い買い替えはしました。
オーディオPCのマザーボードについて
マザーボードはオーディオ向けなら尚更品質にこだわりたいですが、1万~3万辺りだとコレといった感じになれるものはないですね。昔と比べると今はメーカー事の品質や性能差はOC製品でもわかりにくいです。全体的にカバーされてて部品も殆ど見えないですし、品質良さそうなのを選ぼうとすると最近のマザーボードは結構高くなってしまったかなという感じです。
Core i7 が発売された当時は、お店側が日本製コンデンサ使用で品質的に10年以上は動作保証はできるよと勧められ、MSIのBig Bang-Trinergyを購入してその後、Fuzion、Marshal、mpowerとBig Bangシリーズを好んで使っていました。ゲーミング的には良い商品でした。
MSIはたまに品質的にも良く他メーカーと特徴が違うスタンスで商品は出してくれたりはします。1年前にOptix MAG274QRF-QDというPCモニターを購入しましたが、色合い、パフォーマンスも他製品より良く、店舗に置いてあるのに展示してないので他製品が売れなくなるのが困るので展示してないのかなと邪推してしまいました。
MSiのモニターが日本で販売されだしたのがシャープ買収後からなのでシャープ辺りの技術が入ったりしている可能性はあったりするのかもしれないです?
データ移動で音質劣化?
USBケーブルはファイル再生では特に気にしていませんが、データ移動などしてると古いファイルはわかってしまう位には劣化したりしてるので、全体的に保存ファイルはLAN経由でNASにすべて移動させようと思っています。MP3で保存していたファイルは結構ノイズが出る音源が多かったです。
ドライブは普段使うことが殆どなくなってしまいUSB-Cで安定感も向上してきていると思うので外付けタイプにしようかなとは考えています。
世代的なものも出てくるのかもしれませんが、自分の場合はいったんISOファイルで取り込んでからWAVファイルにしたりしてます。
オーディオ専用ミニPCを構築
roon移行も見据えてPCをオーディオ用にACアダプターでmini-itxかMicroATXで組もうかと思っていましたが、12月頃にVivoMini VC65-C1ミニPCを中古で3万円で購入できたので購入しました。
メモリも最近安いタイミングが多く16G×2を1万で購入できたのもよかったです。CPUもTシリーズで消費電力も少なく5w辺りでaudirvana originで問題なく再生できています。CPUも8700tに追加で2万辺りで交換できそうだったのでそのうち安い機会があれば交換予定です。
睡眠時にzenstream経由でタイマーをかけて1時間半ほど曲を流していますが元々使っていたデスクトップは簡易水冷で静かですが起動音が少しでも有るか無いかで音の聞こえ方差は結構あるので今は音楽再生はミニPC、ファイルフォーマットなどはデスクトップPCでやっています。
性能で音質比較であればクアッドチャネルマザーボードとその世代と同じCPUのデュアルチャンネルマザーボードで音質の差の良し悪しが出るのかはメモリのレイテンシの応答速度の差も2倍近くはあるので興味はあります。流石に自分は音楽再生をCPUだけで100w超える消費電力はきついので試そうとは思いませんが、、、
音の出だしで差が出やすい
自分の体感では処理や応答速度などの影響でPC性能で音の出だしは差が出やすいように思えてはいます。
メモリーOCに関しても自動設定のXMPは応答速度が緩く個別調整が必要になるのがテンプレで最適解も組み合わせで個体差があるので、ネイティブメモリーの方が音楽的には安定するんじゃないかなと思います。
ヘッドセットを使ってVCなどをしていた時に、古くなったノートPCや個別のサウンドボード経由からのマイク入力からは声にノイズが入りやすくなったりしていたので、USB経由よりもLAN経由の方がノイズ回避はしやすいように思えます。

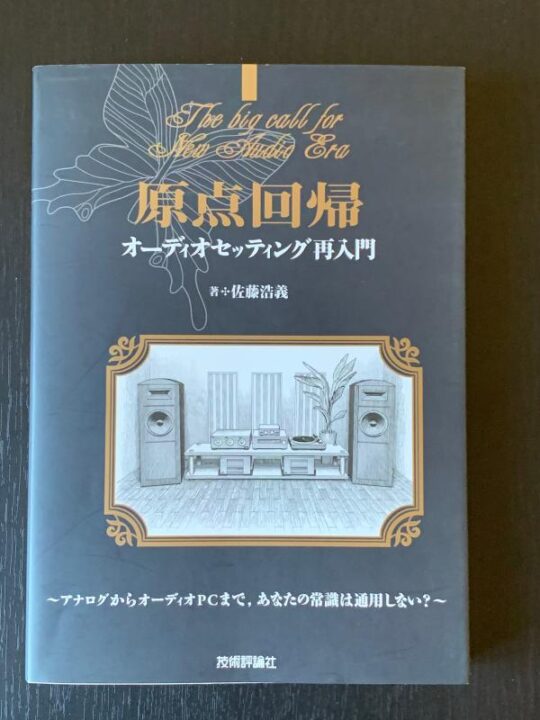

![コルセア CORSAIR 1600W PC電源 AX1600i[ATX/EPS /Titanium] AX1600i CP-9020087-JP](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/r-kojima/cabinet/n0000000487/0843591050326_1.jpg?_ex=128x128)

コメント 他者への誹謗中傷はお控え下さい